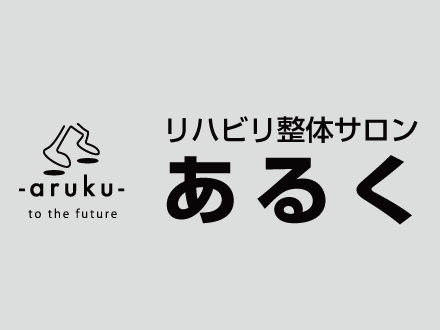【解説】首コリ、首の痛みがつづいたら頚椎症かもしれません!頚椎症を運動学で改善する方法
-1024x683.jpg)
頚椎症(けいついしょう)は、首の骨である頚椎が変形し、神経を圧迫することで起こる病気です。
様々な症状を引き起こしますが、代表的なものとして以下が挙げられます。
「首全体が重く感じたり、時々、鋭く痛む」
「首から肩、腕にかけて痛みやしびれが広がる」
「腕や手がしびれる」
「腕や手の感覚が鈍くなる」
「しびれと同時に手の力が入らない」
もし、これらの症状があれば、もしかしたら頚椎症が原因かもしれません。
私たち『リハビリ整体サロンあるく』に来院される、頚椎症の患者さんたちの実際の訴えをご紹介します。
「5年以上前に首コリ、首の痛み(頚椎症)と診断され、MRIで椎間孔が狭くなっていると診断される。3年前からはめまいが出現。1日中デスクワークなので首コリ、めまい、頭痛、いらいら、だるさ、目の疲れなどで全体的にやる気がでず、精神的にも気分も乗らないことが多い」
「首コリ、肩こりがひどい。自律神経の乱れや不調も感じる。漢方や薬を飲んでも改善せず、頭も働かず、緊張や不安が強く、精神的な落ち込みが仕事に影響して困っている」
「長年、首・肩の痛みに悩まされており、むち打ちになってさらにひどくなった。星状神経節ブロックや硬膜外ブロック注射をするも副反応に苦しみ、改善しない。仕事上、下を向くことが多く、ひどいときは何をしていても、じっとしていても、寝ていても痛い。仕事も休んでしまうので迷惑をかけてしまっているので、困ってる」
「 首コリ、首の痛み(頚椎症)で、首・肩こりがひどく痛い。朝起きると首が突っ張っていたり、ひどいと首がロックされて動かせない。首コリでイライラしたり、夜も痛みで起きてしまったり、眠りが浅く、質も悪いので困っている」
このような症状を感じたら、早めに専門家にご相談ください。
目次
1.頚椎症の代表的な症状
.jpg)
(1)痛み
首の痛み
首全体が重く感じたり、特定の部位に鋭い痛みを感じたりします。
肩や腕の痛み
首から肩、腕にかけて痛みやしびれが広がることもあります。
(2)しびれ
腕や手のしびれ
特定の指先がしびれたり、感覚が鈍くなることがあります。
手の力が入らない
しびれと同時に、手が痺れて力が入りにくいことがあります。
(3)その他の症状
- 頭痛・後頭部痛:後頭部やこめかみに痛みを感じることがあります。
- めまい:立ちくらみや、回転性のめまいを感じることもあります。
- 吐き気:めまいに伴い、吐き気を感じる場合もあります。
- 集中力の低下:頭がぼーっとしたり、集中できなくなったりします。
- 不眠:痛みや不快感で夜中に目が覚めてしまい、睡眠の質が低下します。
- イライラ感:痛みによるストレスから、イライラしやすくなります。
- 疲労感:全身のだるさや疲労感を感じることもあります。
(4)症状が悪化する要因
長時間のデスクワーク
猫背姿勢や同じ姿勢を長時間続けることで、頚椎への負担が増加します。
ストレス
ストレスは筋肉を緊張させ、血行不良を引き起こし、症状を悪化させることがあります。
運動不足
筋肉が硬くなり、関節の動きが悪くなることで、症状を悪化させることがあります。
間違った寝姿勢
高すぎる枕や硬すぎるマットレスは、頚椎の自然なカーブを崩し、症状を悪化させることがあります。
2.なぜ、頚椎症になるのか?
.jpg)
頚椎症は、首の骨である頚椎が変形し、神経を圧迫することで起こる病気です。
では、なぜ頚椎症になってしまうのでしょうか?
主な原因として、以下のものが挙げられます。
(1)加齢
椎間板の変性
年齢とともに、椎骨と椎骨の間にある椎間板が変性し、弾力性を失います。
これにより、クッション性が低下し、骨同士が擦れ合うことで神経を圧迫することがあります。
骨棘の形成
椎骨の縁に骨が出っ張り(骨棘)ができ、神経を圧迫することがあります。
(2)姿勢の悪さ
猫背
猫背の姿勢は、頚椎に負担をかけやすく、変形を早める原因となります。
長時間の同じ姿勢
デスクワークなどで長時間同じ姿勢を続けると、特定の部位に負担がかかり、変形を促進する可能性があります。
(3)外傷
むち打ち症
交通事故などで首に強い衝撃を受けると、頚椎が損傷し、将来的な変形のリスクが高まります。
(4)その他
先天的な異常
頚椎の形状に生まれつき異常があり、症状が出る場合があります。
重いものを持ち上げる作業
首に負担がかかる作業は、変形を促進する可能性があります。
(5)頚椎症が進むと…
頚椎症が進行すると、神経が強く圧迫され、以下のような症状がさらに悪化することがあります。
- しびれ:手足のしびれが強くなり、日常生活に支障が出てしまいます。
- 運動麻痺:手足が動きにくくなることがあります。
- 排尿・排便障害:重症になると、排尿や排便に困難が生じる場合もあります。
3.頚椎症への医学と運動学の違い
-1024x576.jpg)
頚椎症の治療には、医学的なアプローチと運動学的なアプローチの2つの側面があります。
それぞれが異なる視点からアプローチすることで、より効果的な治療が可能となります。
(1)医学的なアプローチ
医学的なアプローチは、病気を治療することを主眼に置きます。
原因の特定
MRI、CTなどの画像診断を用いて、頚椎の変形や神経の圧迫といった原因を特定します。
薬物療法
痛みや炎症を抑えるための鎮痛剤や消炎鎮痛剤、筋肉の緊張を緩めるための筋肉弛緩剤などが処方されます。
手術療法
神経圧迫が強い場合や、保存療法で改善が見られない場合は、手術による治療が検討されます。
(2)運動学的なアプローチ
運動学的なアプローチは、体の動きや機能を改善することを主眼に置きます。
姿勢評価
猫背やストレートネックなど、不良な姿勢を評価し、原因となる筋肉の緊張や柔軟性の低下を特定します。
運動療法
痛みを軽減し、筋肉のバランスを整えるための運動療法を行います。
ストレッチ、筋力トレーニング、体幹トレーニングなどが代表的です。
機能回復
日常生活動作の改善や、スポーツ復帰など、患者さんの目標に合わせた機能回復を支援します。
(3)医学と運動学の連携
医学と運動学は、それぞれが補い合うことで、より効果的な治療が可能になります。
痛みを軽減しながら機能回復
薬物療法で痛みを抑えつつ、運動療法で機能回復を図ることで、より早く日常生活に戻ることができます。
再発防止
運動療法により、姿勢や体幹の安定性を高めることで、再発を予防することができます。
手術後のリハビリ
手術後も、運動療法によって早期回復を促し、生活の質の向上を図ることができます。
(4)どちらを選ぶべきか?
どちらのアプローチが適切かは、個々の患者さんの症状や状態によって異なります。
医師や理学療法士などの専門家と相談し、自分に合った治療法を選ぶことが大切です。
頚椎症の治療は、医学的な治療と運動学的な治療を組み合わせることで、より良い結果が期待できます。
4.人にやさしい運動学による 頚椎症へのアプローチ
-576x1024.jpeg)
頚椎症の改善には、医学的な治療に加えて、運動学に基づいたアプローチが非常に有効です。
運動学は、人間の動きや機能を科学的に研究する学問で、その知識を活かして、痛みを軽減し、機能回復を促すことができます。
運動学に基づいたアプローチは、頚椎症の痛みを軽減し、機能回復を促す上で非常に有効です。
しかし、個々の状態によって適切な運動は異なります。
必ず専門家の指導の下で行うようにしましょう。


(首コリ)-440x330.jpg)
②-440x330.jpg)
-440x330.jpg)